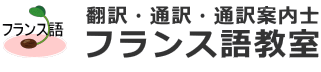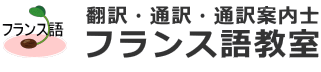|
|
黒い聖母
ホテルで荷を解いて、日暮れまではまだだいぶありそうだったので、聖域Sanctuaireに登ってみることにした。聖域へはホテルの前から急な石段が続いている。登りはじめてすぐ気がついたのは、黒味がかった石灰岩の石段の表面にアンモナイトや矢石などの化石が露出していることだった。12世紀以来、巡礼者たちが許しを請いつつ膝だけで登ったという石段は磨かれたようになっている。216段の石段を登りきるとそこが聖域だ。サン・ソヴール・バジリカBasilique
St-Sauveur、ノートル・ダム礼拝堂Chapelle Notre-Dame、サン・ミッシェル礼拝堂Chapelle St-Michelと三つの教会が寄り添うように建てられているが、開いていたのはノートル・ダム礼拝堂だけだった。このシャペルはまたの名を「奇跡の礼拝堂」Chapelle
miraculeuseという。ここの黒い聖母に会うためにはるばるやってきたのだ。
「黒い聖母」は、オリエント世界における大地母神が初期キリスト教に取り込まれたものだと言われており、ヨーロッパでは東方キリスト教が伝わった地域に多く残っているというが、ロカマドゥールのものは元来は黒い聖母ではなく、白く化粧され、宝石や宝冠で飾られたものだったという説もある。宝冠が頭に載っている写真も知られているが明らかに後補のもので、現在は何もかぶっていない。確かに写真で見るル・ピュイにある黒い聖母などとはだいぶ雰囲気が違うが、製作年代が違うし、やはり黒い聖母という呼び名のほうが神秘的ではないか。
簡素な木の扉を押して礼拝堂の中に入ると、内部はかなり暗い。目が慣れてくると礼拝堂の一方の壁は岩壁がむき出しになっている。シンプルなデザインのステンドグラス、木組みのベンチや献灯台も質素なつくりで好もしい。折しもヨハネ・パウロ2世への献灯が行われていた。
12世紀の作である胡桃の木像は想像していたよりずっと小さかった。膝に幼子イエスを抱き、少し首をもたげた顔にはアルカイックスマイルにも似た笑みを浮かべている。とても芸術とは呼べないような古拙なものだが、その華奢な体つきと容貌は時空を超えてどこか中宮寺の弥勒をほうふつさせる。信仰心が生み出したものの持つなにかしら人の心に訴えかけてくる力というものは、自分のような無信仰の人間にも素直に理解できるものだ。同じような衝撃を、多感な少年時代に興福寺で出会った阿修羅の前で受けたことをふと思い出して、不思議な気持ちになった。人間の悲しみを凝縮したような阿修羅の貌だちと慈愛の表現である弥勒や聖母、いずれも不安な時代を生き、信仰に心の救いを求めた者の手になるものだ。
フランスの作曲家プーランク(Francis Poulenc 1899-1963)は、1936年にこの黒い聖母に出会って深い感銘を受け、「黒い聖母への連祷」という教会音楽を残した。親友の事故死の悲報に接して、ロカマドゥールへ癒しを求める旅をしたときのことだという。この旅が彼の音楽家人生の大きな転機となり、これ以降プーランクは多くの教会音楽や宗教オペラを作曲している。
|